2016年度 実習生
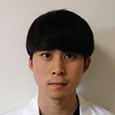 |
H28.5.23 鳥大医学部医学科 6年生 飯田 典之 |
|
一週間、手厚くもてなしていただき、また、たくさんの事をご指導いただき、誠にありがとうございました。今まであまり馴染みがなかった「在宅医療」という形態を実際に目の当たりにして、一医療人としてとても貴重な経験ができたと感じています。 普段、医学を学んでいる中、ある疾患に対して症状、検査、治療、またそれらの診断基準というものを覚える作業をくり返す一方で、実際の医療現場ではそのような典型例ばかりではなく、それどころか、いかに患者さんの生命や健康の全体を診ることができるかという事がとても大切であると思います。 ひだまりクリニックでは訪問看護や訪問介護など他の職種と連携しながら、24時間体制で在宅医療を行えるよう整備されており、身体の状態から、なかなか外来受診ができない患者さんの診察から、急変時の対応、在宅緩和ケアから看取りまで、まさに患者さんとその家族の方々に寄り添った医療が提供されていました。そこでは、病気をただ治療するということだけではなく、患者さんの性格や趣味、好きな事などを把握して、より深い信頼関係を築いたり、家族構成や家族の介護力、家族間の関係性など細かな所にまで目を向けて、患者さんの心理的・社会的側面なども含めて幅広く考慮しながら、個々人に合った総合的な医療の実践がなされており、在宅医療の魅力や重要性に気づかされました。 現在、約8割の人が病院で亡くなっている一方で、6割以上の国民が「終末期の療養はできるだけ自宅で行いたい」と回答したというデータがあります。かくいう私も、最期をどこで迎えたいか?と問われれば、可能な限り自宅が良いと答えます。そのように在宅医療に対するニーズは高く、今後もますますその需要が高まっていくと思います。 在宅で療養したい、人生の最期は愛する家族に見守られ、心からリラックスした状態で迎えたいといった希望を持つ患者さんに、必要かつ十分な医療が供給されるよう、これからもっと医療体制の整備や在宅医療というものの認識が広がることを願っています。 そして、私自身、患者さんの疾患にだけでなく、その背後に広がるさまざまな要因とも向き合い、真に心から寄り添える医師を目指して頑張りたいと思います。 |
|
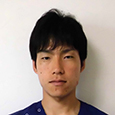 |
H28.5.30 鳥大医学部医学科 6年生 妻鹿 倫征 |
| 御多忙の中、1週間実習をさせていただきありがとうございました。 この度の実習では、外来・通院医療、入院医療に次ぐ第3の医療といわれている在宅医療において、かかりつけ医や訪問看護師の役割であったり、患者さんやご家族の思いに触れる貴重な経験を積むことができました。 特に印象に残ったのは、「先生に来ていただけて本当に安心します。」という患者さんとご家族の声でした。かかりつけ医との間に築き上げられた信頼関係が、闘病・介護生活の不安を癒すことを目の当たりにしました。全人的苦痛という言葉がありますが、私はこれまでの実習の中で、実に様々な苦痛と向き合う方々を目にしてきました。耐え難い痛みのために、死んでしまいたいと口にしたり、家族に当たったりしてしまう患者さんの痛みを抑えることで、生きるために治療を受けてみようと思えたり、支えてくれる家族への感謝の心が戻ったり、という風に、様々な苦痛は複雑に関与し合っているように思います。 医療とは、人それぞれに種類も程度も異なる様々な苦痛を取り除くためにあるのだと改めて思い、あと1年で医師となる身として、その苦痛に向き合う覚悟を新たにしているところです。また、そんな苦痛と24時間365日向き合っておられるかかりつけ医の先生方の下で実習させていただけたことを非常に光栄に思います。 今後もさらに高齢化が進み、地域に密着した医療のニーズは増々増加していくと考えられます。将来、私がどのような立場で医療に従事するにしろ、病院と診療所、福祉、保健、行政等との連携なくしては、良い医療を行うことは難しいと思います。視野の狭い、柔軟性のない医師にならないよう、様々なことにアンテナを立てて色々なことを学び続けていきたいと思います。 |
|
 |
H28.6.20 鳥大医学部医学科 6年生 坂本 有里 |
| ひだまりクリニックでの実習を経て、一週間という短い期間ではありましたが、様々な形の在宅医療を知ることが出来ました。安定している方の訪問診療、往診を要請されての診察と処置、そして在宅での看取りなど、大学病院だけで実習していてはなかなか見ることの出来ない実臨床を学ぶことの出来る貴重な機会でした。 先生が診察に訪れると多くの患者さんが笑顔を浮かべられ、あるいは自分の体調の不調をあれこれと先生に話される姿が印象的でした。どちらの方も先生が診療に来てくれたことに安心し、その発露の方法が笑顔だったり自分の訴えを聞いて欲しいという形になるのかな、と思いました。長く訪問診療を続けて患者さんと先生との関係が確立しているからこそなのだろうと思います。 在宅医療を必要とされている方には外出が難しい方、高齢者向け施設に入所されている方、終末期を自宅で過ごされる方など様々で、その患者さんやご家族の方一人ひとりにそれぞれの事情や考えがあり、私が見ることができたのはほんの一部ではあるとは思いますが、一言ではとても表すことの出来ない奥深さが在宅医療の世界にはあるのだと感じました。 もちろん病院の医療もそれぞれの患者さんに合わせて行われますが、在宅医療では病院において以上に患者さんに合う形の医療が提供出来ること、家族の方も一緒に医療に参加している気持ちが強いことなどが特徴ではないかと思います。多職種の方が患者さんを中心に考えた医療を構築して行く姿は、私が思い描いていた理想の医療そのものでした。 これから自分が医師としてどのような道を進むかはまだわかりませんが、今回見た医療の形を決して忘れることなく、どこまでも患者さんに寄り添う医師でありたいと思います。 今回の実習を受け入れて下さったひだまりクリニックの皆様、そして学生の見学を快く承諾して下さった患者・ご家族の皆様、本当にありがとうございました。 |
|
 |
H28.6.27 鳥大医学部医学科 6年生 進藤 源太朗 |
| この度、大学の臨床実習の一環で在宅医療専門のひだまりクリニックで一週間ほど自習させていただきました。先生方をはじめスタッフのみなさんには丁寧に対応していただき大変お世話になりました。 今回の実習に入るまでは、在宅診療は慢性疾患の患者さんがほとんどで比較的安定しておられる方ばかりというイメージでしたが、実際には急性転化された患者さんも多くいらっしゃり、自分の想像以上にハードな分野だと実感しました。訪問先の患者さんは、先生や看護師さんが来るのを楽しみにしておられ、患者さんやご家族にとって在宅診療が生活の一部になっていると感じました。在宅医療は、一般病院の外来とは異なり自宅に伺うため、ご家族や家庭環境といった患者さんの背景を身近に感じることができます。患者さんの背景を深く理解し、患者さんや家族にとってよりよい方法を他の医療スタッフと探っていくのが在宅医療の醍醐味だと思いました。また、患者さんに関わる全ての医療スタッフと密に連携をとることの重要さを痛感しました。 在宅医療を必要とする患者さんは今後増加していくことが予想されます。ひだまりクリニックは、今後広まっていくと予想される在宅医療のひとつのモデルになっていくと思いました。そうした場所で一週間も実習させていただき非常にありがたかったです。 医学を学んでいると病気に対して検査、治療することに終始しがちですが、それだけでは多くの患者さんの思いに応えることはできません。今後こうした思いに応えるためには、自分がどの分野に進もうとも、在宅医療について理解しておかなければならないと感じました。 今回学んだ在宅医療の考えを踏まえ、患者さんにとってよりよい医療を提供できるよう深く学んでいきたいと思います。 最後になりましたが、ひだまりクリニックのスタッフのみなさん、患者さん、そしてご家族の方には実習を受け入れてくださり大変感謝しております。ありがとうございました。 |
|
 |
H28.7.19 鳥大医学部医学科 6年生 野波 啓樹 |
| 鳥取に来てから地域の住民さん方との交流や健康活動を通じ、患者さんと近い位置で支えられる医師となれたら、と今日考えるまでに至りました。そういった意味で大変興味のある分野で実習できたことに感謝しております。 実際のところ、まだまだ在宅医療への理解は浸透しているとまでは言えません。それは自分にも言えたことでして、実際のところどのようなことをされているか、その仕組みはどうなっているか、といった具体的なイメージは曖昧なままでした。確かに、過去何件か同行させていただいたことはありますが、まだ低学年であったことで医学的・社会福祉的知識が不足していて満足いくまでには把握できておりませんでした。老老介護の現場を見ても、その過酷さは理解できても、その仕組み・背景に至るまで考えを巡らすには力不足であったと言わざるを得なかったのです。今回、6年生として改めて在宅医療の実際を見学させていただき、得るものは非常に大きかったと考えます。月並みですが、訪問を通して強く感じたことを挙げさせて頂きますと、「患者様とご家族が主役であること」「家族の数だけ事情があること」「在宅だから見られる笑顔があること」という点について考えさせられました。 レクチャーではシステムやクリニックの立ち位置について基本的なところから解説していただき、スムーズに実習を吸収することができました。当初、朝カンファはただただ圧倒されていただけでしたが、日を重ねるにつれ、情報共有の“効率の良さと重要性”が分かってまいりました。一方道中では、在宅のメリット・デメリット、困難なケースや今までの歩みのお話し等、在宅医療に関するお話・裏話が聞けて非常に興味深かったです。 今回、4日間という短い期間でしたが在宅医療の雰囲気を知ることができました。緩和に限らず在宅医療の実際を見たい・知りたいという目標を達成できたのではと思います。これも親身に対応してくださったスタッフの皆様や患者様・ご家族様のお蔭です。これからの道に生かせていけるよう、精一杯精進して参ります。本当にお世話になりました、ありがとうございました。 |
|
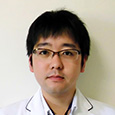 |
H28.7.25 鳥大医学部医学科 6年生 山方 俊弘 |
| 今までの臨床実習は大学病院もしくは市中病院での実習で、患者さんとも診察時しか言葉を交わす機会はなく、生活については表面上のことしか聞いたことはありませんでした。 ですが、患者さんにとって病院での生活は非日常であり、これからの医療に求められるのは患者さんを日常に近い環境に持って行けるかが大切だと思います。今回の実習では、その中心的な役割を担う在宅医療の現場を1週間と限られた時間でしたが、学ばせていただきました。 ひだまりクリニックの先生、看護師の方とご一緒に診療に回らせていただいた患者さんは、お一人で、ご夫婦で、息子・娘夫婦と住んでおられる方など様々おられました。どの方も笑顔でリラックスして、時にはご家族にもわがままなんかもおっしゃりながら楽しく生活を送られていました。介護の辛さというのは書籍での知識しかありませんが、ご家族にとっても相当大変なことだとおもいます。けれども、お孫さんとご一緒に笑っておられる方、趣味に興じておられる方、どのご家庭にも笑顔がありました。その笑顔を絶やさないためには、医師や看護師、薬剤師、介護士、リハビリスタッフ、ケアマネ等多くの方々で連携し、ご家族の皆様をサポートすることが不可欠です。多職種連携が成功してこそ、患者さんの日常があるのだと痛感した1週間でした。 私が生まれたときには最期は病院でという風潮があり、家で最期を看取ることは少なくなっていました。「死ぬときぐらい好きにさせてよ」樹木希林さんのお言葉ですが、家で最期を希望される方が多くなってきた現在では、患者さんの希望する最期を迎えるためにも在宅医療の重要性は日に日に増してきます。在宅医療をするにあたって医師には、医学的知識以外にも介護分野、行政分野等幅広い知識が必用となってくると思います。この1週間では、介護サービスが十分に受けられない方に対して、担当のケアマネさんと連携をして、医師として何ができるのかも学ばせていただきました。私の将来の目標は在宅医になることです。今回の貴重な1週間の実習で「見て」、「聞いて」、「知った」ことを忘れずにおきたいと思います。ひだまりクリニックの皆様、実習にご協力いただいた患者さんとご家族の皆様、多くのことを学ばせていただきありがとうございました。 |
|
 |
H28.10.12 鳥大医学部医学科 4年生 井上 望 |
|
私は今回のひだまりクリニックさんでの実習をとても楽しみにしていました。実際に在宅医療を経験したことがありませんでしたし、在宅医療という分野に興味があったからです。 まず思ったのが、朝のカンファレンスの雰囲気がとても明るいなということです。患者さん一人ひとりの状況を職員の皆さんが共有していて、全員でお話をされているのが印象深かったです。そのカンファレンスの中で、亡くなられた方のお家に行ってきました、という報告があったことに驚きました。在宅医療は患者さんが亡くなられてもそこで終了ではないのですね。医者は病気を診るのではなく、患者さんを診るのだとよく聞きますが、まさにこういうことだと思いました。 カンファレンスのあとに様々なお家や施設に連れて行っていただきましたが、時間が限られている中でも、必要な検査や診察を手早く行い、そして、しっかりと患者さんの話を聞いておられる姿に感動しました。また、ひだまりクリニックの先生方は地域の方に非常に信頼されていて、患者さんやその家族、また施設の職員にとっても心の拠り所になっているように感じました。このように地域の人々の心に寄り添い、密着した医療こそ、地域医療だと思いましたし、今回の実習のテーマである、患者中心の医療だと思いました。 移動中の車の中でいろいろなお話をしていただいたのも印象に残っています。少し残念だったのが、私たちが事前にいただいた日程には先生方の地域医療についての講義の時間が30分取ってあったのですが、それがなくなってしまったことです。もっとたくさんお話を聞いておけばよかったなと少し悔やんでおります。しかし、職員の皆さんに本当に優しく接していただき、非常に有意義な実習をさせていただきましたこと、感謝しております。ありがとうございました。 |
|
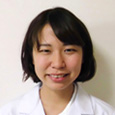 |
H28.10.12 鳥大医学部医学科 4年生 上田 絵美子 |
|
今回の実習では、患者さんの「病気を治す」ことだけでなく、「看取る」ことにも目を向けた在宅医療を1日見学させていただきました。医師の役割の中で看取ることもとても大切であることを先生に教えていただきましたが、これまでそういう風に考えたことのなかった私にとってとても心に残る話になりました。 往診の中で、先生も看護師さんも、患者さんやご家族との距離が物理的にも精神的にも近かったことが印象的でした。特にそれを強く感じたのが話し方です。言葉遣いも何も敬語に限ったことはなく、方言を混じえて話すことで親しみやすい雰囲気を作っていらっしゃって、患者さんももちろんですが、ご家族も先生や看護師さんに信頼をおいているのを感じました。私もそのように患者さんやご家族に信頼してもらえる医師になりたいと感じました。 また、触診から縫合等の手技、肝疾患から皮膚疾患まで様々な分野にまたいで医療を行う総合的な力が必要になることや、他職種との連携が非常に重要であることが興味深かったです。 |
|
 |
H28.10.19 鳥大医学部医学科 4年生 宮元 大央 |
|
まず始めに、本日は一日ありがとうございました。 訪問診療を専門にされているクリニックということで、私が今まで見学させて頂く機会のあった病院とは、また違った体験をさせて頂きました。学内での講義の中でも、訪問診療というものを耳にすることはあったのですが、実際にはどのようなことをされているのか不明瞭なままであったため、今回の実習で訪問診療の一端に触れることができ、多くのことを実感しました。 少子高齢化が進む日本の現代社会において、老老介護というものは避けては通れないものであり、訪問診療はその一助を担っているものであると思います。しかし、訪問診療というものは、全国的に見ても認知度はあまり高くはなく、それを専門とする医師も多くはないというのが現状です。それは、医療従事者の持っている曖昧な死生観、そして医師としての“心”というものに起因しているものであると思います。一人では動くこともままならず、食事をすることも、自発呼吸もできない状況の中で、延命行為を行うことに一体どのような意味があるのか。一人一人の医療従事者が、“死”というもの、そして“生”というものに真摯に向き合っていくことでしか、現在の状況は変わらないのだと感じました。 今後、私達が社会、そして医療を展開していく時に再び直面するであろう現実を感じさせていただく一日でした。働く場所は違えど、働く科は違えど、医療を施していく者として、現在の状況を見つめ、考えていきたいと思います。 |
|
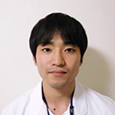 |
H28.10.26 鳥大医学部医学科 4年生 紙谷 亮 |
|
この度は、地域医療体験実習として受け入れていただきありがとうございます。今回の実習では一日のみの参加となりましたが、今までに在宅医療に触れる機会がなかったため に多くのことを学ぶ貴重な体験となりました。 地域医療体験実習を行うにあたり、患者中心の医療とはどのようなものかを考えながら見学しました。患者さんのご自宅や施設への診療・治療を見学して感じたことは、先生の患者さんへのコミュニケーションの取り方です。在宅医療で診療を行う方の中には、なかなか会話をすることができない方も多くおられました。その中で先生は丁寧に話しかけてうなずきを見たりしながら、その時の体調を判断しておられました。また患者さんだけでなく、一番近くで見ておられるそのご家族と密に会話を交わすことで、診療・治療にあたっており、これもまた患者中心の医療なのだなと感じました。 患者さんもご家族も笑顔になるためには、患者さんの病状・体調がよくなること、安定することはもちろんですが、患者さんやご家族との関係性が非常に重要なのだと思います。先生や看護師の接し方を間近で見ることで感じとることができ、今回の実習に参加しければわからないことでした。このような貴重な体験をさせていただき、院長、副院長先生をはじめ、スタッフの方には大変感謝しております。今回学んだことを忘れず、患者中心の医療を実践できる医師になれるよう努力し続けたいと思います。 |
|
 |
H28.10.26 鳥大医学部医学科 4年生 船津 のぞみ |
|
私は今回の実習で初めて在宅医療がどういうものであるのか理解することができました。在宅療養支援診療所であるひだまりクリニックは、在宅医療に特化しており、先進的で貴重な取り組みをしていらっしゃる病院だと思いました。 現在の日本は高齢化が進んできており、今まで当然とされていた「入院療養、外来診療」は少しずつ「在宅医療」へ転換している状況で、在宅医療のニーズが社会全体で高まってきているのは本当だなと感じました。 また今回の実習で、在宅医療を行うには病院側が介護士さんや福祉の方々と密に連携をとりながら、病院で行う医療と同様の医療を在宅で行うこと、家族が主役となり患者さんを支えていく介護力が非常に重要となることを身に染みて感じました。そして外来診療と異なり、在宅医療では患者さんの家に医療チームが向かうので、アウェーな状態で一から信頼関係を築き上げていくことがとても難しそうだなと思いましたが、先生方と患者さんは限られた時間の中でコミュニケーションをとりながら医療だけでなく安心も提供しているように感じました。 チーム医療というものも在宅医療において重要だと思いました。同じ時間に全員で集まることが難しいため患者さんの自宅においておくノートに共有事項を書いていたり、移動する間にも電話で密に連携をとっていて、見えないところでのつながりを感じました。 私も将来患者さんとの強い信頼関係を築き上げて安心する医療を提供できるようになりたいと思いました。 この度は貴重な体験をさせて頂き本当にありがとうございました。 |
|
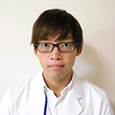 |
H28.11.2 鳥大医学部医学科 4年生 宗村 佑人 |
|
実習を行う前に在宅診療について考えていたことは、病院で入院することと比べると、入院した方が、検査や設備は充実していて、食事などによる栄養面は、しっかり管理され、万が一の急変の際にも、素早く対応が行えるなどの特徴があると考えていました。在宅診療は、長年住み慣れた家にそのままいれることにより、これまで通りの自分らしい生活を継続でき、「やすらぎ」や「安心感」など精神面が支えられるなどの特徴があると考えていました。 午前中の在宅診療に同行させてもらって感じたことを3つ挙げます。 1つ目は、患者さんが活発的な人が多かったことです。在宅診療を利用する患者さんは寝たきりが多いイメージでしたが、実際はそういうわけでもなく、大山に行く人、農業をする人、川でカニを捕る人などその人らしい生活を送っているようでした。 2つ目は、患者さんの家族も治療行為に参加することがあることです。今回は患者さんの点滴が終わったら、家族の方がチューブを抜くことでした。家族の方も治療行為に参加することで、家族の方しか気づかないような小さな変化への対応も行うことができるようになると思いました。 3つ目は、医師、看護師、薬剤師、介護士、ケアマネージャーなどの多職種の方たちに加えて患者さんとその家族を含めた今後の方針などを話し合う場があることを初めて知りました。今までの実習では、多職種の方たちで患者さんのことを話し合い、みていくことが「チーム医療」だと思っていましたが、患者さんと家族を含めたものこそが「チーム医療」だと考え直しました。 在宅診療と入院にはそれぞれの良い点があり、どっちの方が絶対に良いと言えるものではないと思います。在宅診療については、まだ知らないことがたくさんあるので、大学生活の残り2年間、医師になってからも学んでいきたいと思いました。 |
|
 |
H28.11.2 鳥大医学部医学科 4年生 矢野 悠介 |
|
今回の実習では、在宅医療を専門に扱っていらっしゃるひだまりクリニックで在宅医療の実際の現場を体験させていただきました。私自身、在宅医療について詳しくは知らなかったこともあり、新たに気付くことが多い実習になりました。 これまで持っていた在宅医療のイメージは、終末期に自宅へ帰ることを希望する患者さんに対して看取りを行うというものしかありませんでしたが、必ずしも終末期の患者さんだけが対象となるわけではなく、認知症や後遺症のある方など、様々な状態の方々が対象になっていることが分かりました。また、24時間の診療体制があることや、訪問看護などの他の職種の人々とも連携することで、想像していたよりずっと充実した医療が提供されていることが印象に残りました。 これから先、さらに高齢化が進んでいく中で、在宅医療の需要は今以上に増加していくと思います。今回ひだまりクリニックのみなさんの在宅医療に同行させていただき、精力的で丁寧な在宅医療の現場を知ることができました。将来私が在宅医療を希望する患者さんに出会った時にも、自信を持って在宅医療を薦めることができると思います。お忙しい中、実習を受け入れていただき、ありがとうございました。 |
|